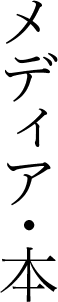美術手帖 2012年5月号
【月評45回】 佐藤溪のなかのシャーマン 佐藤溪「旅立ちのとき」展
前から訪ねてみたかった大分の由布院美術館が3月いっぱいで閉まることを知り、あわてて時間を捻出し九州に飛んだ。
霧のかかる小雨のなか、初めて訪ねた湯布院で、その美術館は実にこじんまりと看板を出していた。しかし、中に入って驚いた。象設計集団の手で20年前に設計されたこの建物は、事前に見ていた写真などからは想像もつかないくらい複合的に練られた施設で、真ん中に広く取られた中庭をグルリと囲み、とりどりの趣向を凝らした展示室やカフェが廊下のようだが、上に登ると由布院の街を一望できる。借景となる由布岳の眺めが気象で刻々と移り変わり、いつまでいても見飽きない。日本にこんなすばらしい美術館があったとは。まずそのことを驚かされた。
しかし、そもそもの動機は美術館とは別だった。湯布院でわずか42歳の若さで他界した放浪の画家にして詩人、佐藤溪の作品をしっかり見届けることにあった。佐藤溪の絵は以前、東京ステーションギャラリーなどで紹介され、多少の注目を浴びたことはあるが、依然として研究の進まぬ、しかしきわめて重要な近代日本の洋画家である。
その重要性は、村上槐多や長谷川利行と比べても、まったく遜色がないであろう。あるいは、その半生と照らし合わせたとき、さらに重要な可能性さえ出てきている。由布院美術館は個人美術館ながら、その作品をほぼ網羅的に収蔵した、きわめて貴重な施設なのである。
語るべきことは多い。が、今回は個人的に関心の強かった佐藤溪とシャーマニズムとの繋がりについて触れておきたい。
最初の紹介者と言ってもよい洲之内徹も指摘していた通り、佐藤溪にはよく知られた紀行的な風景画とはまったく異なる、妖気的な一群の絵が存在する。これらはおそらく、大本教からの影響だろう。知人の紹介で亀岡の大本教本部を訪ねた佐藤溪は、そこに長期滞在し機関誌の表紙に絵を提供した。信者ではなかったようだが、深い影響を受けたことは、中央アジアの風俗や装飾、シャーマニズムに着想したと思しき一連の画面にあらわれている。実際、大本教のカリスマであった出口王仁三郎は戦前に大陸に渡り、この地を放浪して歩いている。
また長く謎であった傑作肖像画《富士恵像》と《蒙古の女》は似ても似つかぬ容貌だが、これは佐藤溪が大本教に滞在した時期に被っており、以前、美術館を訪ねた信徒の方によると、描かれた女性はいずれも、佐藤溪に連れ添った妻のような女性を描いたものらしい、と高橋鴿子館長は語ってくれた(ちなみに佐藤溪は生涯、独身であった。)
あの慈愛に満ちた《富士恵像》(その肩のラインは富士山の裾野を思わせる)と鬼神さえ思わせる《蒙古の女》(後ろに描かれた文字は一体なんだろうか)が、同時期(1950年)に描かれた同一人物だって?僕はにわかに目を疑った。が、じっくり絵を見ているうちに、次第に理解できるような気がした。そのことについては、また機会をあらためることにしよう。
PROFILE
さわらぎ・のい
美術評論家 1962年生まれ
主著に『日本・現代・美術』『戦争と万博』『太郎と爆発』